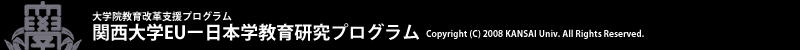日本の古典文学、中でも平安時代の和歌、物語、漢詩などを研究しています。よく知られた作品名で言えば、『古今和歌集』『伊勢物語』『うつほ物語』『源氏物語』『更級日記』『菅家文草』などですが、特に『伊勢物語』を中心に、さまざまな問題に取り組んでいます。平安時代の文学は、ながらく規範として読み継がれ、後代の日本文学、日本文化の源泉として重要な役割をはたしてきましたが、、そのような視点から、注釈史や享受史の研究にも取り組んでいます。また、日本の文学をそれだけで考えるのでなく、中国を中心にした東アジアという、国際的文化の広がりの中で考えることの必要性を重視し、おもに日本と中国の文化的交流の姿についても考え続けています。 |
||
平安時代の文学は、早くから絵に描かれ、絵と一体化した形で享受されてきました。現存する作品は平安時代末期以降のものですが、その図柄や場面構成を通して、我々は、各時代の人々の作品理解の姿を具体的にうかがうことができます。ヨーロッパには、ダブリンのチェスター・ビーティー・コレクションなど、日本の絵入り本のすぐれたコレクションがあります。それらを紹介しながら、絵を通して作品を読むことを試みたいと思います。 |
||
私たちは、他者という鏡にうつった自分を見て、他人の目に自分はそう見えるのかと、その意外な姿に驚くことがある。というよりも、それがわかるようになってはじめて、人間は一人前の大人になったと言える。日本の文学や文化についても、自分たちだけでわかったつもりになっていることが、まだどんなに多いことか。ヨーロッパという異文化の中で、日本の文学や文化はどう受け止められているか。それを学ぶことによって、気づかなかった本当の日本が、私たちの前に姿を見せるだろう。 |
||