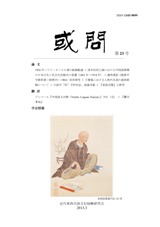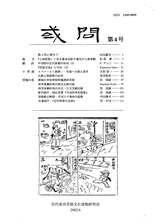或問-WAKUMON
近代東西言語文化接触研究会の会誌:『或問』 since 2000.10.1
第47号(2025.6) / 第46号(2024.12) / 第45号(2024.6) / 第44号(2023.12) / 第43号(2023.6) / 第42号(2022.12) / 第41号(2022.6) / 第40号(2021.12) / 第39号(2021.6) / 第38号(2020.12) / 第37号(2020.6) / 第36号(2019.12) / 第35号(2019.6) / 第34号(2018.12) / 第33号(2018.6) / 第32号(2017.12) / 第31号(2017.6) / 第30号(2016.12) / 第29号(2016.6) / 第28号(2015.12) / 第27号(2015.6) / 第26号(2014.12) / 第25号(2014.6) / 第24号(2013.12) / 第23号(2013.3) / 第22号(2012.10) / 第21号(2011.12) / 第20号(2011.7) / 第19号(2010.12) / 第18号(2010.7) / 第17号(2009.12) / 第16号(2009.7) / 第15号(2008.12) / 第14号(2008.7) / 第13号(2007.10) / 第12号(2006.12) / 第11号(2006.6) / 第10号(2005.11) / 第9号(2005.5) / 第8号(2004.10) / 第7号(2004.1) / 第6号(2003.5) / 第5号(2003.1) / 第4号(2002.6) / 第3号(2001.11) / 第2号(2001.3) / 第1号(2000.10) /
或問第47号(2025.6)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 石崎汽船株式会社の航路案内 | 松浦 章 | 1 |
| 『日本国語大辞典』第3版への期待 | 田野村忠温 | 17 |
| 郭実猟《万国地理全集》地名研究 | 莊 钦永 | 45 |
| 近代国別化漢語商務教材的詞彙教学範式研究:以《清語教科書》為为中心 | 莫 崇遠/楊 帥可 | 67 |
| 哲学術語「意識」的生成与演変 | 彭 兵/朱 棠 | 81 |
| 石山福治《支那語辭彙》(1904)中的仮名注音標記法 | 李 晶鑫 | 93 |
| 鲍康寧《一个老伝教士給侄子的信》研究 | 鄒 王番 |
113 |
| 德富蘇峰的中国游記 | 劉 紅 | 125 |
| 《法国人用漢語口語教科書》中的法語遷移与依存語法思想研究 | 王 海姣 |
133 |
| 論李賀詩韻脚的韻律風格 | 欧 晴/王 思齐 | 145 |
| 目的論視角下的中国電影字幕日訳研究——以電影《赤壁》的語言外文化能指(ECR)為例 | 羅 佳穎/劉 孟洋 | 153 |
| 中国語「脏」と「污」の多義性と社会文化的基盤 | 劉 赫洋 | 165 |
| 武侠小説与浪漫小説詞彙特徴対比分析 | 王 麗娟/孫 曦宇 | 175 |
| 蘭学資料校訳注(八):『采覧異言』『西洋紀聞』(五) | 徐 克偉 | 181 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第46号(2024.12)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 江戸時代の河岸問屋と清代中国の碼頭貨棧 | 松浦 章 | 1 |
| 奥地利藏《坤舆万国全图》的版本问题 | 王 耀 | 15 |
| 「卡車」の語史──その起源と展開 | 田野村忠温 | 31 |
| 《海国图志》初刻本刊行年代新考 | 荘 欽永 | 47 |
| “脾”的词义分化 | 黄 河清 | 57 |
| 最高程度を表す副詞の日中比較――「一番」「最も」と“最”“顶”を中心に | 陳建明/楊梓琪 | 65 |
| 中国向地中海:一种新的视角 | 海 風 |
73 |
| 佐藤一斋和来舶清人的交流 | 舒 志田 | 79 |
| 日本古代国家の政治形態に関する研究 | 婁 雨婷 |
97 |
| 从圣谕宣讲到官民传达:清代圣谕讲解书与白话告示 | 王 婷 | 105 |
| “分词”考源 | 佟 芸辰 | 117 |
| 《从接触语言学角度看现代汉语中的俄语借词》述评 | 王 秋霞 | 129 |
| 蘭学資料校訳注(七):『采覧異言』『西洋紀聞』(四) | 徐 克偉 | 133 |
| 卡薩納特図書館(羅馬)及其中国文献:査找指南 | 梅欧金著/内田慶市・高昌旭訳 | 141 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第45号(2024.6)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 日本語の中国地名の変遷──その多様性と類型 | 田野村忠温 | 1 |
| 從“Œcologie”至「生態」/「生態學」的翻譯之旅 | 郭 詩玲 | 25 |
| “電子”一詞的訳定歴程及其意義引申 | 李 志良 | 45 |
| 塑造自我:晚清域外游記中的“中華聖教” | 張 萍 | 57 |
| 知青作家回憶録的代際特点與歴史反思──以老鬼、梁暁声、王安憶為例 | 史婷婷/肖玲玲 |
69 |
| 《天工開物》東伝日本及其科技詞彙受容実証研究 | 李紅/賈瓊 | 81 |
| 盗屍謡言:協和剖屍案與1933年解剖規則之修訂 | 林 夢月 |
93 |
| 日本殖民時代在沖縄與台湾初期実行的日語教育之対比考察──以教科書和教員為線索 | 楊 雪 | 109 |
| 蘭学資料校訳注(六):『采覧異言』『西洋紀聞』(三) | 徐 克偉 | 123 |
| 『西学一斑周伝』(5-7) | 陳 暁淇 | 131 |
| 『知説』(3-5) | 沈 国威 | 141 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第44号(2023.12)
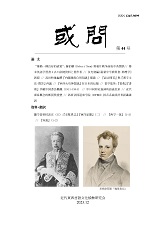
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| “推動一種良好的感覚”:羅伯聃(Robert Thom)與鴉片戦争前後中英関係釈 | 王 宏志 | 1 |
| 幕末英語学習書4点の依拠資料と著作者──『英米対話捷径』『和英商賈対話集』『商用通語』『ゑんぎりしことば』 | 田野村忠温 | 19 |
| 伍光建編《最新中学教科書·物理学》新探 | 王广超/呉暁斌 | 43 |
| 高田時雄編撰『内藤湖南自用印譜』補遺 | 石 暁軍 | 55 |
| 『語言問答』與『漢字文法•問答』再議 | 宋 桔 |
75 |
| 『西洋火攻神器説』在日本的伝播 | 舒 志田 | 93 |
| 書学集英:『書苑』『書菀』刊載中国書法概観(1911-1944) | 蘇浩/邱吉 |
109 |
| 中日同形近義詞的語義色彩 | 花 蕾 | 123 |
| 近代霍乱概念的断裂與重塑──基于『駐華医報撮要』的考察 | 王 海姣 | 141 |
| 試析法国遠東学院(EFEO)拼音系統設計者認識訛誤 | 董 嘉夢 | 159 |
| 蘭学資料校訳注(五):『采覧異言』『西洋紀聞』(二) | 徐 克偉 | 169 |
| 『西学一斑周伝』(1-3) | 陳 暁淇 | 175 |
| 『知説』(1-2) | 沈 国威 | 183 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第43号(2023.6)
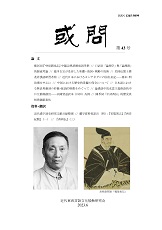
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 衛匡国『中国新図志』中越辺界誤解成因考釈 | 林 宏 | 1 |
| 日訳名「論理学」與「論理術」的源流考論 | 甘 進 | 23 |
| 徳川吉宗が受容した和蘭・清国・朝鮮の馬術 | 許 浩 | 33 |
| 美国伝教士賽兆祥漢語研習考察 | 鄒王番/施正宇 | 53 |
| 近代日本におけるモンテネグロの国名表記――幕末・明治期を中心に | 中澤拓哉 |
63 |
| 中国における歴史的景観の保全について | 曹 婷 | 79 |
| 日本語における無活用動詞の形態・統語的特徴をめぐって | 袁 建華 |
91 |
| 論漢語中馬克思主義術語的中日互動與創出——以陳望道訳本(1920)為例 | 劉 孟洋 | 107 |
| 陳季同「中詩西伝」的歴史真相與価値重估 | 尹徳翔/ I. 奥特森 | 117 |
| 近代漢字詞史研究文献目録整理 | 楊 馳 | 113 |
| 蘭学資料校訳注(四):『采覧異言』『西洋紀聞』(一) | 徐 克偉 | 143 |
| 『西周伝』(三) | 李心羽/張厚泉 | 151 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第42号(2022.12)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙・>目次 | ||
| 『海録』諸版とその系譜 | 田野村忠温 | 1 |
| 日常之思:晚清域外游記中的“郷愁” | 張 萍 | 17 |
| 戴季陶的日語学習法及対現代日語教学的啓示 | 孔 穎 | 29 |
| 記一幅稀見的花瓣式世界地図────関於日本蔵『西洋進貢地体圓球全図』的研討 | 王 耀 | 35 |
| 他山之石:近現代日本美術史界対中国書画的研究 | 蘇浩/黎菁予 |
49 |
| 赫士:近代高等教育理念在中国的早期伝播 | 郭 建福 | 61 |
| 『瀛寰志略』中的国名訳詞考析 | 沈 和 |
71 |
| “灰闌故事”在中德之間的流伝 | 王 鈺玨 | 89 |
| 衆情與个情:黄宗羲“万古之性情”説的内涵與理路 | 莫 涯 | 101 |
| 德編教材『漢語通釈』識小 | 何 玉潔 | 113 |
| 魯迅『四日』転訳底本考 | 陳 暁淇 | 123 |
| 語言接触與現代漢語詞彙体系的建構 | 白楊/蘇鷹 | 133 |
| 中国語の外来語 | 張芃蕾/鈴木武生 | 149 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第41号(2022.6)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 試探中西文化交流中中国対羅馬法的継受:以早期中文羅馬法教科書中対11至19世紀欧州羅馬法学歴史沿革的論術為例 | 臘 蘭 | 1 |
| 張 萍 | 21 | |
| 中日両国法律用語的交流與互鑑──以刑名術語為例 | 鄭 艶 | 31 |
| 西学科技漢籍東伝與日本近代思潮──以『博物新編』為例 | 李 紅/任 紅磊 | 41 |
| 呉嘉善『翻訳小補』編輯與出版考 | 潘 瑞芳 |
51 |
| 文墨相輝:刻石文的語譯與域外之音 | 郭 鐘蔚 | 63 |
| Parler et style chinois: innovation and recovery of late Qing manuals of Chinese | Gabriele Tola |
75 |
| 近代日本語における「消費」の成立──幕末・明治期の経済学書を中心に | 楊 馳 | 87 |
| 「もっと」と動詞の否定形との共起について | 曹 婷 | 103 |
| 近代西洋料理解説書『西法食譜』に関する考察 | 楊 一鳴 | 113 |
| 『公余瑣談』及其対話教学初探 | 王 海姣 | 123 |
| 音訳と意訳──概念の体系化と歴史 | 田野村 忠温 | 141 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第40号(2021.12)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 清代康熙年間の徽州官吏と洞庭湖の湖盗 | 松浦 章 | 1 |
| 田野村忠温 | 13 | |
| 法国国家図書館所蔵明清西人漢語学習文献述略──従傅爾蒙目録到儒蓮目録的考察 | 李 真 | 27 |
| 『鄂羅斯番語』に見られる“了”“力”“拉”の用法について | 萩原 亮 | 37 |
| 陜西・山西における漢画像石の雲気文装飾について彙 | 李 宸鋭 |
49 |
| 1875年に撤去された宗教施設としての中国式灯台――西嶼塔燈 | 大西蘭ほか | 59 |
| 『官話指南』中的“把”字句句型研究――與同時期中国報刊雑誌的比較 | 楊 昕 |
81 |
| 佐藤春夫訳『聊斎志異』に関する研究――固有の言葉の訳し方を中心に | 劉 陽 | 97 |
| 陳春生が主筆した『通問報』についての考察 | 喬 昭 | 113 |
| 翻訳資料 | ||
| 『西周伝』(二) | 李心羽・張厚泉 | 127 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第39号(2021.6)
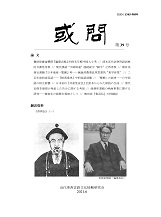
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙・目次 | ||
| 襄助徐継畬撰研『瀛環志略』的佚名年軽中国人小考 | 莊 欽永 | 1 |
| 鄭艶・張莉 | 23 | |
| 現代漢語“字詞相通”連続統中“動字”之再考察 | 劉 赫洋 | 33 |
| 康有為進呈書籍『日本地産一覧圖』考――兼論其農業改革思想的“東学背景” | 朱 夢中 | 47 |
| 二百年前的客家話――『岭南逸史』中的客語詞彙 | 王思斉・廖佳儀 |
63 |
| 「摩擦」の語史――日中両語の相互影響 | 崔 蕭寒 | 75 |
| 日本初の『共産党宣言』全訳本からみた術語の生成 | 劉 孟洋 |
93 |
| 清代官僚李璋煜が発給した告示に関する考察 | 王 婷 | 107 |
| 商務印書館の映画事業に関する研究――陳春生の経歴を視座として | 喬 昭 | 123 |
| 増田渉『魯迅伝』の校勘記 | 東 延欣 | 137 |
| 翻訳資料 | ||
| 『西周伝』(一) | 李心羽・張厚泉 | 149 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第38号(2020.12)
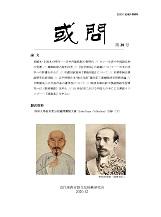
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 長崎丸・上海丸の時代――日中汽船航路の新時代 | 松浦 章 | 1 |
| 田野村忠温 | 15 | |
魏源岭南之游年份考 |
莊 欽永 | 27 |
『医学原始』の語彙について――日本の洋学への影響を中心に |
舒 志田 | 39 |
中露対訳資料『華俄初語』について |
萩原 亮 | 55 |
来華耶穌会漢語研究伝統述略 |
李 真 | 67 |
| 江戸時期日本“独立学派”儒学家三浦梅園詩学思想述論 | 張 雨軒 | 73 |
矢野龍渓三大代表作品の継承性について |
周 艶君 | 83 |
晚清来華伝教士漢語熟語学習研究――以《教務雑誌》為中心 |
鄒 王番 | 97 |
| 近19世紀末における中国人の手による漢訳イソップ――『読書楽』を中心に | 陳 旭 | 107 |
| 加州大學柏克萊分校藏傅蘭雅文庫(John Fryer Collection)目錄(下) | 千葉謙悟 | 119 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第37号(2020.6)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 王 宏志 | 1 | |
| 松浦 章 | 17 | |
| 王 広超 | 31 | |
| 田野村忠温 | 41 | |
19世紀末20世紀初中西文化交流:《十二表法》在中国 |
Lara Colangelo[腊蘭] | 61 |
知識遷移:漢蘭書籍在德川日本的輸入 |
舶 威廉 | 79 |
從《臺灣語虎之卷》看教材中的話語與權力 |
楊 承淑 | 95 |
日本の歴史的環境保全に関する研究――古都京都を事例として |
曹 婷 | 105 |
| 馬国賢及其対漢語在欧洲伝播所做出的貢献 | 李 思漢 | 115 |
The Study On the Translation of Geographical Terms of Chinese Monthly Magazine(《察世俗每月統記伝》) |
楊帥可/王思斉 | 139 |
三門湾事件時期『申報』所見対意大利的公衆情緒 |
Vinci Renata[海風] | 151 |
| 近代中日間の社会主義術語の交流に関する一考察――趙必振訳《近世社会主義》(1903)を中心に | 劉孟洋/徐昊 | 159 |
| 清末中国画報における西洋医学の発展 | 鄧 怡然 | 171 |
| 『朝日新聞』「主題談話室・戦争」中的戦争体験、情感記憶 | 方 光鋭 | 185 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第36号(2019.12)
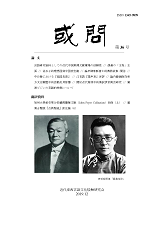
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙と目次 | ||
言語研究資料としての近代中国地理文献彙集の信頼性──『海国図志』と『小方壺斎輿地叢鈔』 |
田野村忠温 | 1 |
|
――満州事変から盧溝橋事件初期まで |
劉 紅 | 11 |
|
――浅談19世紀中西方文化関係之変遷 |
李 真 | 27 |
| 彭 強 | 39 | |
| 中日韓における『経国美談』 | 周 艶君 | 55 |
| 江有誥『諧声表』述評 | 王 思斉 | 59 |
|
――以『東方文化聯盟会志』為中心 |
劉 重越 | 79 |
|
――以『蒙学報』為中心 |
陳 旭 | 93 |
| 満洲ピジンの音韻的特徴について | 萩原 亮 | 105 |
| 加州大學柏克萊分校藏傅蘭雅文庫(John Fryer Collection)目錄(上) | 千葉謙悟 | 115 |
| 満漢合璧版『古新聖経』訳注稿(6) | 竹越孝・斉燦・余雅婷・陳暁 | 145 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第35号(2019.6)
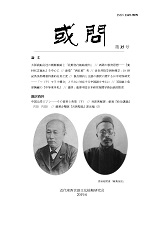
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙と目次 | ||
| 大阪商船会社の朝鮮航路と「北鮮急行航路案内」 | 松浦 章 | 1 |
| 西周の教育思想――『養材私言稿本』を中心に | 張 厚泉 | 18 |
| “番茄”“西紅柿”考 | 黄 河清 | 31 |
| 王 広超 | 21 | |
| 視点制約と主語の選択に関する日中対照研究 ――「~(テ)モラウ構文」とそれに対応する中国語を中心に |
張 芃蕾 | 49 |
| 王国維と桑原隲藏の『中等東洋史』 | 陳 琳琳 | 59 |
| 書評:重建中国日本研究相関学術伝統的探索 | 趙 暁靚 | 79 |
| 中国沿岸ピジン――その資料と背景(下) | 萩原 亮 | 83 |
| 対訳與解読:厳復『政治講義』(VII)(VIII) | 沈国威/郭玉紅 | 99 |
| 満漢合璧版『古新聖経』訳注稿(5) | 竹越孝・斉燦・余雅婷・陳暁 | 129 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第34号(2018.12)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙と目次 | ||
| 十七史商榷と近藤正斎 | 松浦 章 | 1 |
| “普通”考 | 黄 河清 | 17 |
| 李紅/于博川 | 21 | |
| 近代米中平等互恵関係の構築に関する蒲安臣の功績 ――清国使節団出発前後の米紙の報道” |
黄 逸 | 31 |
| 中国語教育関係書の『萬物聲音』と『北京語の味』における擬声語について | 李 夫平 | 43 |
| The Finals System of the Tang Dynasty in Northern China in Mahā-mayūrīvidyārājan | WANG Siqi / YANG Shuaike | 57 |
| 山本竟山と富岡鉄斎の交遊について | 蘇 浩 | 71 |
| 《史記》中的漢文帝立儲 | 董 成龍 | 79 |
| 江戸幕府禁止輸入部分漢籍及其政策1630-1720 | 徐 克偉 | 83 |
| 中国沿岸ピジン――その資料と背景(上) | 萩原 亮 | 93 |
| 対訳與解読:厳復『政治講義』(V)(VI) | 沈国威/郭玉紅 | 107 |
| 満漢合璧版『古新聖経』訳注稿(4) | 竹越孝・斉燦・余雅婷・陳暁 | 135 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第33号(2018.6)
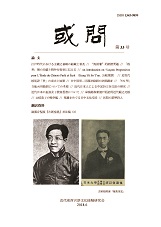
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙と目次 | ||
| 江戸時代における王羲之書跡の舶載と普及 | 松浦 章 | 1 |
| “馬鈴薯”的詞源問題 | 黄 河清 | 13 |
| 陶 徳民 | 19 | |
| An Introduction on “Leçons Progressives pour L’Étude du Chinois Parlé et Écrit(Kung Yü So T’an. 公餘瑣談)” | 牧野格子 | 27 |
| 近現代接尾辞「者」の成立と展開 | 朱 暁平 | 39 |
| 日中同形二字漢語動詞の語源調査 | 楊 馳 | 51 |
| 「VN型」自他両用動詞についての考察――自動詞文の種類を中心に | 徐 媛 | 65 |
| 近代日本人による中国語口語文法の研究――介詞に関する記述を中心に | 盧 驍 | 77 |
| 近代日本の皇族女子教育思想について――下田歌子著『内親王殿下御教育意見』を手掛かりして | 孫 東芳 | 91 |
| 辜鸿铭和新渡户稻造的近代観之比較――以《中国人的精神》和《武士道》為例 | 李 凱航 | 103 |
| 山崎豊子の戦争観――『不毛地帯』を中心に | 李 瑞華 | 113 |
| 梵鐘をめぐる日中文化交渉――杭州岳王廟鐘を中心に | 邱 吉 | 129 |
| 民間の遊歴詩人――柏木如亭 | 陳 慧慧 | 135 |
| 満漢合璧版『古新聖経』訳注稿(3) | 竹越孝・斉燦・余雅婷・陳暁 | 151 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第32号(2017.12)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 清代中国の朝貢国と互市国 | 松浦 章 | 1 |
| 「邪教」在行動――河南某高校「呼喊派」傳教案剖析 | 劉 平 | 13 |
| 崔 学森 | 25 | |
| 専門語から一般語へと――積極・消極を中心に | 王 麗娟 | 35 |
| 梁啓超の翻訳活動について――1900年前後の翻訳活動を中心に | 仲 玉花 | 45 |
| 初版『漢英合壁相連字彙』の考察 | 李 晶鑫 | 57 |
| 近代詞彙的環流――以「冒険」為例 | 崔 恵善 | 73 |
| 中国語辞典『四声標註支那官話字典』の考察 | 王 雪 | 85 |
| 三島由紀夫『午後の曳航』論――少年による猫殺しをめぐって | 朱 田雲 | 97 |
| 『假面自白』的虚與実――三島由紀夫文学的原点 | 李 凱航 | 109 |
| 『実学報』における日本の新聞記事の翻訳について――『中外商業新報』掲載「廣東金礦の發見」を例に | 陳 静静 | 119 |
| 黎子鵬著『福音演義』・李雪濤著『思想断章』 | 沈 国威 | 137 |
| 対譯與解読:厳復『政治講義』(IV) | 沈国威・郭玉紅 | 139 |
| 満漢合璧版『古新聖経』訳注稿(2) | 竹越孝・斉燦・余雅婷・陳暁 | 157 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第31号(2017.6)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 江戸時代唐船齎來の『唐詩選』とその再版本 | 松浦 章 | 1 |
| 民国時代における日本研究雑誌の濫觴 | 霍 耀林 | 15 |
| The transplantation and adaptation of terms from Japan to China at the beginning of the 20th century | 真田治子 | 31 |
| 『植物名実図考』在近代中日間的流播 | 梁 従国 | 47 |
| 『天主実義』の初期刊本とその改訂をめぐって | 王 雯璐 | 63 |
| 重訳《俄国情史》をめぐって——「自由結婚」と革命 | 清地ゆき子 | 71 |
| 漢語“有V”與日語「Vてある」的対比研究 | 黄利斌/李広志 | 87 |
| 明治末期における言語学と人種論の交錯 | 李 凱航 | 99 |
| 清末の中国人が編纂した日本語教科書における文法教育——内容、方法と理念 | 劉 賢 | 113 |
| 『共産党宣言』における訳語の中日両言語間の交渉——「Bourgeois」の訳語を中心に | 劉 孟洋 | 133 |
| Theology訳詞在中日的生成與発展 | 王 彩芹 | 151 |
| 《何明華與中國關係之研究(1922-1966)》評介 | 應 煥強 | 161 |
| 対譯與解読:厳復『政治講義』(III) | 沈国威・郭玉紅 | 167 |
| 満漢合璧版『古新聖経』訳注稿(1) | 竹越孝・斉燦・余雅婷・陳暁 | 183 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第30号(2016.12)
.jpg)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 日治時代台湾烏龍茶の海外輸出と汽船 | 松浦 章 | 1 |
| 衝撃-回応説的社会史闡釈——重読魏斐德『大門口的陌生人』 | 李 雪濤 | 19 |
| 従『史記』文本内考論漢高祖生年問題 | 王 強 | 39 |
| 以"巨眼"為中心的明代私家書法鑑蔵 | 張 氷 | 51 |
| 托马斯·珀西的中国研究芻議——以『中国詩文雑著』為中心 | 李 真 | 63 |
| 『官話文法』——日本漢語教学語法的萌芽 | 楊 杏紅 | 71 |
| 基于認知視角下的敬語教学探析—以『綜合日語』為例 | 侯 占彩 | 81 |
| 王桐龄之赴日経歴及日本相関著述考 | 霍 耀林 | 91 |
| A Vocabulary of the Shanghai Dialectにおける用字用語について | 張 厚泉 | 103 |
| 転訳博物学:明治初期博物局編『博物図』を例として | 邢 鑫 | 115 |
| 対譯與解読:厳復『政治講義』(II) | 沈国威・郭玉紅 | 127 |
| 蘭学資料校譯注(三):『顕微鏡記』及其他 | 徐 克偉 | 145 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第29号(2016.6)
.jpg)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 五四運動と日清汽船会社 | 松浦 章 | 1 |
| 英語在十九世紀上海的社会伝播:受衆、空間及場域 | 司 佳 | 19 |
| 江沙維手稿之考証————有関対漢語語法的分析 | 朱 鳳 | 29 |
| 海内奇観:空前興盛的明代書法交易 | 張 氷 | 41 |
| 赫士譯編『光学揭要』初歩研究 | 王 广超 | 53 |
| 明治時代における日本人が編纂した中国語辞典の研究 | 王 雪 | 69 |
| 『厚生新編』にみる蘭学音訳語とその漢字選択 | 徐 克偉 | 83 |
| 「教練」の語誌的研究——日中比較の視点から見る語義の変遷と転換 | 仇 子揚 | 99 |
| 清代中国書法対朝鮮王朝的影響——以金阮堂為中心 | 曹 悦 | 119 |
| 学習者向けの中国語教育における語彙シラバスの作成原則に関する研究 | 楊 帥可 | 131 |
| 日中における「契約」の使用と定着に関する一考察 | 吉田慶子 | 141 |
| 清末"速成式"日語教材的教学理念——以『日語独習書』和『日語捷径』為例 | 劉 賢 | 157 |
| 「陰極」「陽極」から見た中日言語交渉 | 王 麗娟 | 167 |
| 明治以降の漢語形容動詞の発達について | 周 菁 | 179 |
| 対譯與解読:厳復『政治講義』(I) | 沈国威・郭玉紅 | 191 |
| 馬若瑟(Prémare)『漢語劄記(Notitia Linguae Sinicae)』第二部訳注(III) | 千葉謙悟 | 211 |
| 蘭学資料校譯注(二):越俎弄筆 | 徐 克偉 | 229 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第28号(2015.12)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 嶋谷汽船会社と日本海定期航路 | 松浦 章 | 1 |
| 近代基督教《三字経》與中西語言文化接触 | 司 佳 | 15 |
| 空海的飛行三鈷杵與寧波之縁 | 李 広志 | 33 |
| 試論来華耶穌会士的中国植物学研究——以卜弥格、韓国英為例 | 李 真 | 43 |
| 近代日語詞彙体系型化過程中漢語同構現象解析 | 李 紅 | 53 |
| "広告"一詞在漢字文化圈内的演変 | 謝薇・羅俊 | 61 |
| 清末至民国早期的翻訳規範(1895-1930)対胡適翻訳小説的影響 | 呉 礼敬 | 73 |
| 日本語の婉曲表現における断りについての考察 | 馮晶・徐千恵 | 85 |
| 《植物学》卷八"分科"考 | 邢 鑫 | 95 |
| 《北京官話全編》方所時間介詞及対象介詞考察 | 斉 燦 | 107 |
| 日本近代軍事用語の成立に資する漢籍とその語彙 | 仇 子揚 | 117 |
| 羅存徳與19世紀50年代的香港教育 | 賀 楠 | 133 |
| 『博物新編』及び中の物理用語について | 王 麗娟 | 139 |
| 従語言接触的角度看現代蒙古語的詞彙 | 来 小子 | 149 |
| 大韓帝国時期(1897-1910)傳入朝鮮的梁啓超著作 | 崔 恵善 | 159 |
| 唐代書家李陽冰篆書書法的復興及其影響 | 曹 悦 | 169 |
| 江沙維《漢字文法》序言 | 王銘宇・盧春暉 | 177 |
| 民国以後的傅蘭雅 | 趙 中亜 | 187 |
| 蘭学資料校訳注(一):天地二球用法序 | 徐 克偉 | 193 |
| 馬若瑟(Prémare)『漢語劄記(Notitia Linguae Sinicae)』第二部訳注(II) | 千葉謙悟 | 197 |
| 『中日近代新詞詞源詞典』の編纂について | 沈国威 | 225 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第27号(2015.6)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 南洋郵船会社の航路案内 | 松浦 章 | 1 |
| 中国"近代史框架"的意識形態化問題 | 劉 平 | 21 |
| 近世中日儒学鬼神論序説 | 傅 錫洪 | 31 |
| 停滞的帝国:西方衝撃的歴史意義 | 張 萍 | 43 |
| 何启、胡礼垣行迹述考 | 張 仲民 | 63 |
| 以漢外詞彙教学為目的之同義詞詞典初探 | 楊 帥可 | 77 |
| 日本語心理動詞の深層格の複合性 | 趙 仲 | 91 |
| 日本博物学史的近世起源 | 邢 鑫 | 101 |
| 馬若瑟(Prémare)『漢語劄記(Notitia Linguae Sinicae)』第二部訳注(I) | 千葉謙悟 | 117 |
| 『和蘭醫事問答』(二) | 徐 克偉 | 145 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第26号(2014.12)

| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 原田汽船会社と青島航路 | 松浦 章 | 1 |
| The Terminological Battle for 'Air' in Modern China | Rune Svarverud | 23 |
| 和製英語「デパート」考 | 王 敏東 | 31 |
| 『談天』中西方天文学名詞的漢譯 | 陳婷・呂凌峰 | 43 |
| 『遐邇貫珍』載「生物総論」及其術語 | 邢 鑫 | 61 |
| 明治日本の中国窯業調査記——景徳鎮の地理状況と製品輸送 | 郭 楠 | 77 |
| 中日米における魯迅とキリスト教の研究について | 陳 維 | 87 |
| 日中同形語の量的分析 | 許 雪華 | 103 |
| 作為文学術語的"背景":以郁達夫為説 | 孫 芸鋮 | 117 |
| 『和蘭醫事問答』(一) | 徐 克偉 | 133 |
| 国際研討会参加記 | 賀 楠 | 145 |
| 裏表紙3 | ||
| 裏表紙4 |
或問第25号(2014.6)
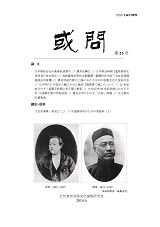
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 日本郵船会社の桑港航路案内 | 松浦 章 | 1 |
| 譯本的轉生——清末時新小説對《天路歷程》的重寫 | 黎子鵬、鄺智良 | 15 |
| 日本明治時期《重修植物名実図考》版本考述 | 梁 従国 | 31 |
| 浅談羅馬法原始文献翻譯:翻譯作品中拉丁文対法律漢語語法的影響 | 臘 蘭 | 43 |
| 清末民国初期の上海における日本の医薬会社の宣伝広告 | 謝 薇 | 61 |
| 江戸時代に中国から輸入された集帖『顔真卿三稿』について | 馬 成芬 | 77 |
| 19世紀末20世紀初期における日本•中国華北間の汽船航路 | 楊 蕾 | 87 |
| 魯迅文学における「自覚」試論——竹内好の『魯迅』を中心に | 陳 維 | 103 |
| 文化遺民的遺與逸——以胡思敬為例 | 呉 晗怡 | 117 |
| 翻訳:百学連環・哲学(二) | 徐 克偉 | 133 |
| 中国語研究のための原資料(1)――「尾崎實旧蔵書」目録 | 氷野善寛、氷野歩 | 145 |
或問第24号(2013.12)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 大阪商船会社の瀬戸内海航路案内——東アジア海域の汽船運航データー | 松浦 章 | 1 |
| モリソンの書簡についての研究——Joshua Marshmanとの確執 | 朱 鳳 | 17 |
| 日本における「動産・不動産」の定着に関する一考察 | 鄭 艶 | 31 |
| “経世”與“体用”:晩清域外游記中的“器物” | 張 萍 | 47 |
| 被遮蔽的声音:辛亥革命後的“剪辫不易服”討論 | 張 希 | 61 |
| 日本明治時期漢語教科書與晩清北京景象——以《官話指南》為中心 | 徐 麗 | 73 |
| 20世紀前半のタイ国華字新聞に見る華人教育 | 王 竹敏 | 83 |
| 20世紀初期における青島と仁川間の汽船航路 | 楊 蕾 | 97 |
| 16-19世紀西方有関中国語言的文献書目初探——以考狄《西人論中国書目》為中心 | 李 真 | 107 |
| 日本統治時代台湾における日本人エリートの海外経験について | 卞 鳳奎 | 117 |
| 双音節化與漢語的近代演進:胡以魯“漢語後天発展論”的啓示 | 沈 国威 | 139 |
| 近代道教文化嬗変的歴史啓示 | 劉 平 | 155 |
| 清末民初《申報》載「新名詞」史料(1) | 沈 国威 | 169 |
| 翻訳:百学連環・哲学 | 徐 克偉 | 181 |
| 学会情報・其他 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 東アジア文化交渉学会第6回年次大会(於上海復旦大学) | 106 |
或問第23号(2013.3)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 1856年ハワイ・ホノルル港の船舶航運(付表) | 松浦 章 | 1 |
| 清末民初上海における中国語新聞の日本広告と社会生活様式の変遷(1861年~1914年) | 謝 薇 | 29 |
| 謝洪賚訳《最新中学教科書・物理学》(1904)初歩研究 | 王 広超 | 43 |
| 万葉集における人称代名詞の連体修飾について――中国語欧化文法を考える一視点 | 稲垣智恵 | 55 |
| 日語中“的”字的句法、語義功能 | 李 金蓮 | 79 |
| 『東語完璧』之研究 | 陳 娟 | 89 |
| 翻訳:プレマール『中国語文注解(Notitia Linguae Sinicae)』(VI)(完) | 千葉謙悟 | 107 |
| 翻訳:『蘭学事始』 | 徐 克偉 | 123 |
| 学会情報・其他 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 東アジア文化交渉学会第5回年次大会(於香港城市大学) | 151 |
或問第22号(2012.10)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 1867年における寧波入港の船舶 | 松浦 章 | 1 |
| 早期入華傳教士的漢語学習観述略 | 李 真 | 13 |
| 簡論晩清游記中的意大利形象—以比較文学形象学的理論為中心 | 25 |
|
| 清末民初の『申報』に見る日本広告について | 謝 薇 | 39 |
| “域”之跨越—以厳復訳介《原富》為例 | 劉 瑾玉 | 53 |
| 《語言自邇集》之協作者 《瀛海筆記》之主角—晩清文化接触中的應龍田 | 宋 桔 | 67 |
| A. D. グリング編、対訳漢和英字書Eclectic Chinese Japanese-English Dictionary(1884)の参考文献をめぐって | 宮田和子 | 79 |
| 劉向《列女傳》在日本的流傳與影響 | 王 恵栄 | 87 |
| 曲尽人去音猶在—《源氏物語》與《金瓶梅》的儒佛思想比較研究 | 徐 麗 | 95 |
| 日本蘭学漢字詞探源 | 何 華珍 | 103 |
| 日本モデルからの離脱—民国初期の教育方針と『新編中華修身教科書』 | 方 光鋭 | 113 |
| 資料:厳復佚文六篇 | 張 仲民 | 131 |
| 挿絵解題:公家書房 | 内田慶市 | 139 |
| 学会情報・其他 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 国際シンポジウム:An International Symposium in Memory of S. W. Williams Relations between East Asia and the United States in the 19th Century | 102 |
或問第21号(2011.12)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 五桂堂印本《澳門番語雑字全本》初探(附影印本文) | 周 振鶴 | 1 |
| 北清輪船公司の汽船による渤海航運について | 松浦 章 | 19 |
| “想像(imagination)”与中日文論的現代性 | 牛 月明 | 35 |
| 17世紀中葉~18世紀中葉における暹羅船の中国・日本への蘇木輸出 | 王 竹敏 | 49 |
| 『海国図志』にみえる「四洲志」の原書をめぐって | 谷口知子 | 59 |
| 黄遵憲“中日同源”論和“西学中源”論的形象学研究 | 張 萍 | 71 |
| 斯賓塞中訳本『肄業要覧』訳詞考 | 王 彩芹 | 91 |
| 耶魯大学衛三畏家族档案所見『聖諭広訓』方言手抄若干種 | 司 佳 | 117 |
| 『或問』の新しい一歩 | 内田慶市 | 131 |
| 学会情報・其他 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 国際シンポジウム:近代東アジアにおける言語接触 | 129 |
或問第20号(2011.7)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 江南製造局草創期に建造された軍艦について | 松浦 章 | 1 |
| 日本漢文小説家的構成及其小説観念 | 羅 小東 | 17 |
| 江南製造局蒸汽機訳著底本考 | 孫壘・呂凌峰 | 33 |
| 19世紀入華宣教師J. L. ネヴィアスの栄光と影 | 宮田和子 | 49 |
| 早期来華耶穌会士対漢語官話語法的研究與貢献 | 李 真 | 59 |
| 論日本漢文小説『新橋八景佳話』的題材特色 | 張 暁青 | 69 |
| 20世紀初期における大阪・大連の汽船航路の研究 | 劉 婧 | 81 |
| 東アジアの表象と造形言語 | 黄 龍求 | 101 |
| 20世紀初期における日本•青島航路の渡航記録 | 楊 蕾 | 113 |
| 王肇鋐の『訳文須知』について | 沈 国威 | 127 |
| 西洋図像新聞に見る中国「刑罰図」 | 陳 其松 | 135 |
| 学会情報・其他 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| シンポジウム報告:日本現代化の歴程、経験及び教訓 | 劉 岳兵 | 149 |
或問第19号(2010.12)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 『甬報』に見る浙江沿海の海盗 | 松浦 章 | 1 |
| 清末佚名『語言問答』研究 | 宋 桔 | 11 |
| 日本人旅行記からみる20世紀前期の大連航路 | 劉 婧 | 27 |
| 雍正六年における暹羅国の中国語通事について | 王 竹敏 | 41 |
| 想像的真實與真實的想像 | 徐 佳貴 | 51 |
| 厳復與復旦公学 | 張 仲民 | 63 |
| 『初學簡徑』:ナポリ版『中国語官話文法』 | 西山美智江 | 81 |
| 翻訳・書評 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| プレマール『中国語文注解』(V) | 千葉謙悟 | 95 |
| 医学・傳教士・現代性—評高晞『德貞傳』 | 劉平・朱丹 | 115 |
| 中国日本思想史研究領域的第一本通史性著作 | 卞 崇道 | 125 |
| 学会情報・其他 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 漢字文化圏近代新語研究会国際シンポジウム開催 | 114 | |
| 表紙絵解題:鄺其照の玄孫からのメール | 内田慶市 | 131 |
或問第18号(2010.7)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 康熙朝内务府商人与日本铜 | 孙 晓莹 | 1 |
| 清末における上海北洋汽船航路 | 松浦 章 | 15 |
| 晩清中央政府の法制官董康の日本監獄視察について | 孔 頴 | 37 |
| 黄远生与《时报》 | 王 红军 | 57 |
| 『新霊枢』が伝えた日本経由の西洋解剖学とその用語 | 松本秀士 | 73 |
| 翻译的政治:“皇”、“王”之论争 | 庄钦永・周清海 | 85 |
| 江戸時代日本における中国語受容の一形態 | 蔡 雅芸 | 127 |
| 从日本调查资料中所见清末民初的中国砂糖业 | 赵 国壮 | 139 |
| 19世紀入華宣教師クローフォードの軌跡 | 宮田和子 | 159 |
| 書評・翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 翻訳語が物語る近代中国の東西言語文化交流 | 塩山正純 | 175 |
| 西周『百学連環』(第一総論) | 沈 国威 | 181 |
| 学会情報・其他 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 出版文化史国際シンポジウム開催 | 158 | |
| 表紙絵解題 | 内田慶市 | 189 |
或問第17号(2009.12)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 十九世紀上半葉基督新教傳教士在漢語詞彙史上之地位 | 莊欽永・周清海 |
1 |
| 1910年代初期における福州と台湾間の帆船航運 | 松浦 章 | 21 |
| 来华耶稣会士的第一篇汉文天主教作品 | 张 西平 | 35 |
| 来华耶稣会士罗明坚的汉语学习 | 张 西平 | 39 |
| 卫三畏与《聊斋志异》 | 顾 钧 | 45 |
| 西医東漸をめぐる「筋」の概念と解剖学用語の変遷 | 松本秀士 | 49 |
| 德国图书馆中文藏书述要 | 杨 慧玲 | 63 |
| 清雍正时代日本铜进口状况——童华《铜政条议》分析 | 孙 晓莹 | 69 |
| 关于清学部编《简易识字课本》(1909) | 沈 国威 | 83 |
| 李善兰・艾约瑟译胡威立《重学》之底本 | 韩 琦 | 101 |
| 沱江流域与潮汕地区的糖业比较(1858-1938) | 赵 国壮 | 113 |
| 学会情報・其他 | - | 頁 |
|---|---|---|
| 世界中国語教育史大会開催 | 柳 若梅 | 135 |
| 2010年の学会情報 | 138 | |
| 表紙絵解題 | 内田慶市 | 139 |
或問第16号(2009.7)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 清朝皇帝康煕帝の訃報と東アジア世界 | 松浦 章 | 1 |
| 訳語「奇跡」と日中語彙交流 | 千葉謙悟 | 19 |
| 「精」の概念をめぐる西医東漸における中国解剖学用語の変遷 | 松本秀士 | 33 |
| 民国时期汉语教学一瞥 | 朱 勇 | 49 |
| 严复《与严修书》日期考订辨讹 | 孫 青 | 55 |
| 马礼逊辞典中的新词语(续) | 黄 河清 | 63 |
| The Chinese Recorderにみるグッドリッチ(富善)とその家族の記録 | 宮田和子 | 73 |
| 近代东亚语境中的日语 | 沈 国威 | 85 |
| 近代中国における日中陶磁器の市場競争について | 馮 赫陽 | 99 |
| 翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 科学术语:目前的分歧与走向统一的途径(傅兰雅) | 孙青/海晓芳 | 117 |
| 学会情報 | - | 頁 |
|---|---|---|
| 東アジア文化交渉学会成立 | 陶 徳民 | 137 |
| 世界漢語教育史研究学会 | 143 | |
| 表紙絵解題 | 内田慶市 | 149 |
或問第15号(2008.12)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 馬禮遜譯『大英国人事略説』探究 | 李 暁傑 | 1 |
| 馬禮遜辞典中的新詞語 | 黄 河清 | 13 |
| 第一本寧波方言英漢詞彙集――『英華仙尼華四雑字文』 | 郭 紅 | 21 |
| 中国における西洋解剖学の受容について――解剖学用語の変遷から | 松本秀士 | 29 |
| 論日本讀本小説『忠臣水滸傳』 | 趙 苗 | 45 |
| 日本とかかわる19世紀中期以前の台湾近代医事の変遷――台湾大学医学部と国防医学院を中心に | 王 敏東 | 55 |
| 日編北京口語教材《官話指南》的語言特点分析 | 呉 麗君 | 65 |
| 日漢辞典的黎明期 | 沈 国威 | 75 |
| 国学扶輪社『文科大辞典』與清末本土経典的“知識資源”転型 | 孫 青 | 85 |
| 『英華萃林韻府』の術語集をめぐって | 宮田和子 | 97 |
| 中国近代新聞と日本新漢字語の導入――日本語記事「清國膠州灣」の中訳を例として | 秦 春芳 | 109 |
| 清中期の袁枚『随園詩話』と市河寛齊編『随園詩鈔』 | 松浦 章 | 125 |
| 試論隋唐以前対西域来華佛教僧侶的漢語教学 | 李 雪涛 | 141 |
| 資料 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| New Publications in Western Languages | Joachim KURTZ | 159 |
| 表紙絵解題 | 内田慶市 | 171 |
或問第14号(2008.7)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 衛生、種族與晩清的消費文化――以報刊広告為中心的討論 | 張 仲民 | 1 |
| 開化期の韓国語における時間表現について――中国語・日本語の時間表現との比較から | 梁 淑珉 | 17 |
| Prémare(1666-1736)のNotitia Linguae Sinicae(1720) | 西山美智江 | 43 |
| 動脈・静脈の概念の初期的流入に関する日中比較研究 | 松本秀士 | 59 |
| 『海国図志・四洲志』に見られる新概念の翻訳 | 谷口知子 | 81 |
| 神戸福建会館與閩南商人 | 王 亦錚 | 99 |
| 関于“和文奇字解”類資料 | 沈 国威 | 117 |
| 另一種秩序、公正與平等――明清秘密教門的信仰與互助 | 劉 平 | 129 |
| 日本漢文小説『啜茗談柄』研究 | 羅 小東 | 145 |
| 秀吉の中国人説について | 鄭 潔西 | 155 |
| 中国語を学んだイギリス東インド会社社員Flintと中国貿易 | 松浦 章 | 165 |
| 翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| プレマール『中国語文注解』(IV) | 千葉謙悟 | 183 |
| 復刻資料・其他 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 助詞的研究 | 博 良勲 | 209 |
| 「助詞的研究」解題 | 内田慶市 | 240 |
| 表紙絵解題 | 内田慶市 | 243 |
或問第13号(2007.10)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 東アジア文化交渉学の対象と方法――グローバルCOEプログラムの開始にあたって | 藤田高夫 | 1 |
| 清朝官吏の見たGeorge Thomas Staunton | 松浦 章 | 9 |
| Guo Liancheng and his Journey to Italy | Miriam CASTORINA | 19 |
| ポストホブソンの中国文西洋医学書 | 松本秀士 | 31 |
| 龙树哲学思想的探源 | 成 建华 | 47 |
| 世界汉语教学史研究综述 | 吴 丽君 | 61 |
| 试论《唐话纂要》的词汇选编特色 | 朱 勇 | 69 |
| 清代沿海商船乗員の見た日本 | 張 新芸 | 75 |
| The Interpretation of Saussure’s Linguistic Ideas in China | Chiara ROMAGNOLI | 87 |
| 道是晴云却雨云——《聊斋志异》早期法译本中对性爱的改写 | 李 金佳 | 99 |
| 翻訳・短信 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 『中国キリスト教美術の起源(1583~1640年)』(IV) | 柏木 治 | 125 |
| 西方汉学史和中西关系史的重要收藏 | 韩 琦 | 133 |
| 文献・資料 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 中国近代的科技术语辞典(1858~1949) | 沈 国威 | 137 |
| New Publications in Western Languages | Joachim KURTZ | 157 |
| 表紙絵解題:防弾チョッキもあるでよ | 内田慶市 | 168 |
或問第12号(2006.12)
| 論文名 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 研究近代東亜報刊史的一些初歩想法 | 潘 光哲 | 1 |
| 人体解剖学の専門書『全体闡微』の解剖学用語について | 松本秀士 | 11 |
| 江戸時代における日本漂着中国人の日本像――筆談資料を中心に | 張 新芸 | 25 |
| 『辞源』與現代漢語新詞 | 沈 国威 | 35 |
| 清代沿海帆船に搭乗した日本漂流民 | 松浦 章 | 59 |
| 翻訳・研究ノート・書評 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 『中国キリスト教美術の起源(1583~1640年)』(III) | 柏木 治 | 69 |
| 康煕『三角形推算法論』簡論 | 王 揚宗 | 117 |
| 日本統治期の台湾での刊行物――日中言語交流の資料として | 王 敏東 | 125 |
| A Thick Description of Traditional Life in Peking.—— A review of Susan Naquin’s Peking: Temples and City Life, 1400-1900. | LIU Ping / FAN Ying | 133 |
| 文献・資料 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| New Publications in Western Languages | Joachim KURTZ | 141 |
或問第11号(2006.6)
| 論文名 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 江戸時代における清朝中国人の画像資料 | 松浦 章 | 1 |
| 抄本《理法器撮要》作者献疑 | 许洁・石云里 | 15 |
| 畢華珍伝稿 | 千葉謙悟 | 15 |
| 唐通事与汉语言文化在日本的传播 | 朱 勇 | 41 |
| 西洋楽理伝来における『律呂正義』続編の役割と影響――その音楽用語を中心ににおける位置 | 朱 鳳 | 51 |
| 中西地理学知识及地理学词汇的交流:艾儒略职方外纪的西方原本 | Paolo DE TROIA | 67 |
| 從「瘟疫」/「黑死病」到「鼠疫」─―中日疾病名稱考源 | 王敏東・蘇仁亮 | 77 |
| Some Preliminary Remarks on the Zhifu Xinshu 致富新書 | Federica CASALIN | 85 |
| ホブソン(合信)にみる解剖学的語彙について | 松本秀士 | 101 |
| 短信・研究ノート | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 19世紀英華字典5種 解題 | 陳力衛・倉島節尚 | 119 |
| 美利坚合众+国,还是合+众国? | 周 振鹤 | 127 |
| 《香港船头货价纸》新探――美国麻省菲利浦斯图书馆访问记 | 陶 徳民 | 129 |
| 黄尊憲的日本語;梁啓超的日本語 | 沈 国威 | 137 |
| The Works of Li Wenyu (1840–1911): Bibliography of a Chinese-Jesuit Publicist | Joachim KURTZ | 149 |
| 関西大学中国語デジタルコンテンツの現状 | 氷野善寛 | 159 |
| 文献・資料 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 表紙絵解題:中国における「写真」――併せて「化学」という言葉について | 内田慶市 | 163 |
| New Publications in Western Languages | Joachim KURTZ | 169 |
或問第10号(2005.11)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 新漢語「大統領」の成立 | 孫 建軍 | 1 |
| 清末の新聞に見る日本汽船の活動 | 松浦 章 | 15 |
| 中華文明上に組み込まれる西洋医学 | 松本秀士 | 29 |
| 初期中国語文法用語の成立 | 朱 鳳 | 47 |
| 和字「腺」の語構成における位置 | 王 敏東 | 65 |
| 清末における西安・咸陽事情 | 張 新芸 | 73 |
| ルイ・バザン『中国語口語の一般原理に関する覚え書』を読む | 小野 文 | 81 |
| 范約翰主編的《小孩月報》首期新探 | 李 暁傑 | 93 |
| 翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 『中国キリスト教美術の起源(1583~1640年)』(II) | 柏木 治訳 | 101 |
| プレマール『中国語文注解』(III) | 千葉謙悟訳 | 121 |
| 『中国語口語の一般原理に関する覚え書』(I) | 小野 文訳 | 145 |
| 研究・資料 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 如何認定Chinese pidgin English | 周 振鶴 | 169 |
| 再論Pidgin English――周振鶴氏への回答 | 内田慶市 | 171 |
| 表紙絵解題:中国人の描いた「ロードス島の巨人像」 | 内田慶市 | 179 |
| 内田发现的抄本《红毛番话》——解题与译解 | 周 振鶴 | 185 |
| 奧地利國家圖書館藏近代漢譯西書 | 沈 国威 | 247 |
| New Publications in Western Languages | Joachim Kurtz | 255 |
| 西学東漸研究の中文・日文文献情報 | 沈 国威 | 261 |
或問第9号(2005.5)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 近代日本語における「時」の獲得 | 松井利彦 | 1 |
| 入華プロテスタント宣教師と日本の書物・西洋の書物 | 八耳俊文 | 27 |
| 上海東文學社與南洋公學的東文學堂 | 鄒 振環 | 43 |
| 從衛三畏檔案看1858年中美之間的基督教弛禁交渉 | 陶 徳民 | 57 |
| 『遐邇貫珍』と幕末に伝えられた太平天国情報 | 松浦 章 | 67 |
| 近代解剖学への萌芽における日中比較身体論 | 松本秀士 | 79 |
| 十九世紀的英語資料與漢語研究 | 内田慶市 | 93 |
| 譯詞與借詞――重讀胡以魯《論譯名》 | 沈 国威 | 103 |
| 翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| プレマール『中国語文注解』(II) | 千葉謙悟訳 | 113 |
| 十字路 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 比钱说第一首汉译英诗还要早的汉译英诗 | 周 振鶴 | 153 |
| 李约瑟文献识小二题 | 王 揚宗 | 157 |
| 西学東漸研究の欧文文献情報 | Joachim Kurtz | 161 |
| 西学東漸研究の中文・日文文献情報 | 沈 国威 | 167 |
或問第8号(2004.10)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 衛匡國的《中國新地圖集》 | F. 馬西尼 | 1 |
| Some notes on translations of the Physics Primer and physical terminology in late Imperial China | Iwo Amelung | 11 |
| The First Chinese Adaptation of Mill’s Logic:John Fryer and his Lixue xuzhi 理學須知 (1898) | Joachim Kurtz | 35 |
| 『全体新論』と『解体新書』(重訂版を含む)との語彙について――日本の洋学から中国への影響の可能性 | 舒 志田 | 53 |
| 明代海外諸国の通事について | 松浦 章 | 75 |
| 翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 『中国キリスト教美術の起源(1583年~1640年)』 | 柏木 治 | 85 |
| プレマール『中国語文注釈』(2) | 千葉謙悟 | 105 |
| 短信・書評 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 晚清翻譯家鍾天緯有關英語教育之佚文 | 周 振鶴 | 141 |
| 《六合叢談》之緣起 | 韓 琦 | 145 |
| 讀[德]李博著《漢語中的馬克思主義術語的起源與作用》中譯本 | 朱 京偉 | 147 |
| 關於古城貞吉的《滬上銷夏錄》 | 沈 国威 | 155 |
| 1819年的兩本西方地理書 | 沈 国威 | 161 |
| 西学東漸研究の欧文文献情報 | Joachim Kurtz | 167 |
| 西学東漸研究の中文・日文文献情報 | 沈 国威 | 175 |
或問第7号(2004.1)
| 論文・翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 19世紀中国“地理大発現”的影響與意義 | 鄒 振環 | 1 |
| 清代広州港の繁栄 | 松浦 章 | 15 |
| 高理文『美理哥合省国志略』 | 李 暁傑 | 27 |
| 台湾の新語・流行語となった日本の漢語 | 王 敏東 | 61 |
| 中国語の近代語彙の形成(4) | F. マシニ | 81 |
| 資料・研究ノート・書評 | 著者 | |
|---|---|---|
| ハーバート燕京図書館蔵キリスト宣教師著述目録続編 | 李 暁傑 | 41 |
| 最近目にした「西学東漸」と言語文化接触に関する書物 | 内田慶市 | 95 |
| “襲猊遺神”:晩清民初的一場話語革命 | 周 振鶴 | 105 |
| 関於『貿易通志』 | 沈国威・王揚宗 | 111 |
| 情報の泉 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 西学東漸研究の欧文文献情報 | Joachim Kurtz | 119 |
| 西学東漸研究の中文・日文文献情報 | 沈 国威 | 125 |
| 表紙絵解題:『紅毛通用番話』について | 内田慶市 | 127 |
或問第6号(2003.6)
| 追悼 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 尾崎實先生を偲ぶ | 尾崎和子 | 1 |
| 内田慶市 北岡正子 西川和男 佐藤晴彦 荒川清秀 周振鶴 塩山正純 奥村佳代子 西山美智江 |
||
| 遺稿 | ||
| 『官話類編』所収方言詞対照表 | 尾崎 實 | 19 |
| 論文・翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 清代の自鳴鐘について | 松浦 章 | 53 |
| 「自転」という語の起源をめぐって | 舒 志田 | 67 |
| 商人・僕人・通事和18世紀中国沿海洋涇浜語的形成 | 司 佳 | 85 |
| 唐話資料の二面性 | 奥村佳代子 | 95 |
| 徐建寅和傅蘭雅『化学分原』的一個譯稿本 | 王 揚宗 | 109 |
| 『官話文法』(1703)補遺 | 西山美智江 | 115 |
| 十字路・情報の泉 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| グラスミア湖の畔にて | 森瀬壽三 | 123 |
| 近代漢字語研究の新機運 | 沈 国威 | 127 |
| 西学東漸研究の欧文文献情報 | Joachim Kurtz | 133 |
| 西学東漸研究の中文・日文文献情報 | 沈 国威 | 136 |
| 表紙絵解題:中国語化されたキリストの一生 | 内田慶市 | 137 |
或問第5号(2003.1)
| 論文名 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 中国語における外国国名表記の固定と変化 | 千葉謙悟 | 1 |
| 日語「女性語」的中訳 | 王 敏東 | 13 |
| 中村敬宇『英華和訳字典』の典拠 | 宮田和子 | 21 |
| 越南語的主要詞彙特徴 | 黄 力游 | 31 |
| 中国語における新語の受容 | 氷野善寛 | 43 |
| 康有為とその日本書目志 | 沈 国威 | 51 |
| 清代の買辧について | 松浦 章 | 69 |
| 翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 『官話文法』(1703)(IV) | F. Varo | 83 |
| 十字路 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 三角帽子雑感 | 萩野脩二 | 105 |
| 東西文化交流の踪跡を探し求めて(I) | 沈 国威 | 109 |
| 西学東漸研究の欧文文献情報 | Joachim Kurtz | 113 |
| 西学東漸研究の中文・日文文献情報 | 沈 国威 | 119 |
| 表紙絵の解題:『小孩月報』に見られるイソップ | 内田慶市 | 123 |
或問第4号(2002.6)
| 論文・翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 第4号に寄せて | 内田慶市 | 1 |
| 『上海新報』に見る幕末官船千歳丸の上海来航 | 松浦章 | 3 |
| 中国語の近代語彙の形成(3) | F. マシニ | 21 |
| 『官話文法』(1703)(3) | F. Varo | 31 |
| 十字路 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| メドハースト雑感--写真への添え書き | 大原信一 | 83 |
| 仏教と耶蘇教の区別 | 青木稔弥 | 85 |
| 情報の泉 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 漢城大学奎章閣所蔵漢訳西書 | 沈国威 | 87 |
| 西学東漸研究の欧文文献情報 | Joachim Kurtz | 97 |
| 西学東漸研究の中文・日文文献情報 | 沈国威 | 101 |
| 新刊紹介:劉広定著『中国科学史論集』 | 沈国威 | 103 |
| 表紙絵の解題:中国コマ漫画の濫觴 | 内田慶市 | 105 |
| 自著紹介:『近代啓蒙の足跡』 | 沈国威 | 111 |
或問第3号(2001.11)
| 論文名 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 越前梅浦岡田家所蔵の「贈倭國難民詩」について | 松浦 章 | 1 |
| 井上哲治郎の『訂増英華字典』に於ける訳語の修整についての考察 | 金 敬雄 | 11 |
| 曹禺初期創作におけるキリスト教の影響 | 姜 小凌 | 23 |
| 評点測議 | 張 小剛 | 33 |
| 晩清における「西学中源」説と「中体西用」論の盛衰について | 王 揚宗 | 45 |
| 翻訳 | 訳者 | 頁 |
|---|---|---|
| 中国語の近代語彙の形成(2) | 沈 国威 | 57 |
| 『官話文法』(1703)(2) | 西山美智江 | 75 |
| 十字路 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| Notes on Late Qing Dictionaries of Physics | Iwo Amelung | 95 |
| 「化石」考源 | 黄 河清 | 101 |
| カガミとメガネ | 谷口知子 | 105 |
或問第2号(2001.3)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 日本語の漢語の書き換えと中国語 | 朱 京偉 | 1 |
| メドハーストの諸辞典とその影響 | 宮田和子 | 13 |
| 誤用例文からみる「把字句」の教授法について | 西川和男 | 23 |
| 『唐話纂要』の言葉 | 奥村佳代子 | 31 |
| 翻訳 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 中国語の近代語彙の形成(1) | F.マシニ | 47 |
| 『官話文法』(1703)(1) | F.Varo | 61 |
| 十字路 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 『山海経』の西漸 | 森瀬壽三 | 69 |
| 上海沙船船主郁松年の蔵書 | 松浦 章 | 73 |
| 岩波文庫『孟子』を疑う | 吾妻重二 | 79 |
| Lo Sem's Role in Early US-Japan Relations | 陶 徳民 | 85 |
| 中国語で最初に牛痘種痘をおこなったAlexander Pearsonのこと | 八耳俊文 | 91 |
| 情報の泉 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 西学東漸研究の欧文文献情報(他) | Joachim Kurtz | 93 |
| 自著紹介:『和製漢語の形成とその展開』 | 陳 力衛 | 99 |
| 抄訳:C. W. Mateer著『官話類編』(1903) | 南部まき他 | 103 |
| 表紙絵の解題 | 内田慶市 | 123 |
或問第1号(創刊号)(2000.10)
| 論文 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 『或問』発刊にあたって | 内田慶市 | 1 |
| 井上哲次郎『訂増英華字典』の典拠 | 宮田和子 | 3 |
| 「望遠鏡」の語誌について | 谷口知子 | 17 |
| 『江鮑笑集』のことば | 西山美智江 | 35 |
| モリソン訳『神天聖書』について | 塩山正純 | 53 |
| 近世唐話学における多様性 | 奥村佳代子 | 69 |
| 十字路 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 羅森来日の契機について | 陶 徳民 | 91 |
| ある出会い | 萩野脩二 | 93 |
| 北京研修を終えて | 西川和男 | 95 |
| わたしと近代日中学術用語の研究 | 荒川清秀 | 97 |
| 情報の泉 | 著者 | 頁 |
|---|---|---|
| 1999-2000年度関係論文 | 沈 国威 | 68 |
| 表紙の挿絵について | 内田慶市 | 99 |